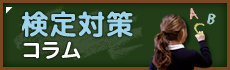エッセー集 イタリア散歩道
シチリア;その混沌とした世界、そして言語
- 小森谷 慶子
- イタリア史研究家Le Ali 6号
シチリアは風光明媚な土地であり、ここで撮影された映画は数多い。様々な映像が脳裏をよぎり、それらを列挙するだけでもこの原稿の文字数は足りないくらいであるが、そのひとつに『カオス・シチリア物語』('84年)がある。戯曲の分野で世界的に名を知られたノーベル賞作家ルイジ・ピランデッロ(1867-1936年)の短編をつなぎあわせ、タヴィアーニ兄弟が映像化したものである。ジュゼッペ・ランチのカメラによって切り取られた鮮烈なシチリアの風景は、昨年の秋、遂にDVD化されたので、写真集の頁をくるように見直すことができるようになった。冒頭では、粗野な羊飼いたちが岩山のような所で卵を温めているカラスを見つけ、そのカラスをいたぶったあげくその首に鈴を結わえて青空に放つと、ニコラ・ピオヴァーニの謎めいた調べとともにカラスがのびのびと翔けながら荒涼としたシチリアの大地を俯瞰し、やがてこつ然とセジェスタの神殿が眼下に現れる…。各挿話は、作家の同時代を扱ったものが主体で、中には作家の母の幼少期にさかのぼるものもあり、衣装などは時代がかっているが、画面に映る田園風景は悠久の時をとどめている。
 コンコルディア神殿の前に立つピランデッロ(アグリジェント1934年)さて、この映画の原作者ピランデッロは、シチリアのジルジェンティ(現アグリジェント)という地で生まれた。アフリカ側の海に面したのどかな田舎町で、ここに残る神殿群がユネスコの世界文化遺産にも指定されていることから今では島内屈指の観光名所のひとつとなっている。その地名は、ギリシアのポリスであった時代にはアクラガス、ローマの支配下ではアグリゲントゥム(農地あるいは農民の意)、アラブ時代にはキルケントあるいはチルチェント、中世以降近世までがジルジェンティで、ムッソリーニの時代に古代ローマふうの今の地名に改名された。このような変遷を見るだけでも変化に富んだシチリアの歴史をうかがい知ることができるだろう。ピランデッロは、少年時代をこの郷里で過ごした後、思春期には家族とともにパレルモへ転居し、パレルモ大学からローマ大学へと移った。大学ではギリシア文学やラテン文学に慣れ親しみ、そこで権威的なラテン文学の教授の不興を買ってローマ大学を逐われることになったが、若いロマンス語の教授の計らいにより、ドイツのボン大学に移ることができ、そこで郷里の俗語についての論文を書いた。イタリア統一運動に際してはマンゾーニらの努力により共通語としてのイタリア語が生まれたが、シチリアから首都に出たピランデッロにとって、地方ごとの多様な話し言葉はひじょうに興味深い研究対象であったことだろう。ローマで文壇にデビューしたピランデッロの小説はもちろんイタリア語で書かれており、当初は新聞や雑誌に掲載されていた。だが、会話の部分にはもちろん地方の話し言葉も用いられているし、言語学者らしい独自の造語もあるので、語形成や語変形などに明るくないと、意味を推量できなかったりする。余談だが、奇しくもピランデッロと同じ年にわが国で生まれた夏目漱石もまた独自の新しい言葉を作り出す名人であったことを思うと、19世紀末から20世紀初頭という激動の時代が、イタリアにおいてもわが国においても、新しい文学における言語形成という面で重要な時代を画したことに改めて思い到る。
コンコルディア神殿の前に立つピランデッロ(アグリジェント1934年)さて、この映画の原作者ピランデッロは、シチリアのジルジェンティ(現アグリジェント)という地で生まれた。アフリカ側の海に面したのどかな田舎町で、ここに残る神殿群がユネスコの世界文化遺産にも指定されていることから今では島内屈指の観光名所のひとつとなっている。その地名は、ギリシアのポリスであった時代にはアクラガス、ローマの支配下ではアグリゲントゥム(農地あるいは農民の意)、アラブ時代にはキルケントあるいはチルチェント、中世以降近世までがジルジェンティで、ムッソリーニの時代に古代ローマふうの今の地名に改名された。このような変遷を見るだけでも変化に富んだシチリアの歴史をうかがい知ることができるだろう。ピランデッロは、少年時代をこの郷里で過ごした後、思春期には家族とともにパレルモへ転居し、パレルモ大学からローマ大学へと移った。大学ではギリシア文学やラテン文学に慣れ親しみ、そこで権威的なラテン文学の教授の不興を買ってローマ大学を逐われることになったが、若いロマンス語の教授の計らいにより、ドイツのボン大学に移ることができ、そこで郷里の俗語についての論文を書いた。イタリア統一運動に際してはマンゾーニらの努力により共通語としてのイタリア語が生まれたが、シチリアから首都に出たピランデッロにとって、地方ごとの多様な話し言葉はひじょうに興味深い研究対象であったことだろう。ローマで文壇にデビューしたピランデッロの小説はもちろんイタリア語で書かれており、当初は新聞や雑誌に掲載されていた。だが、会話の部分にはもちろん地方の話し言葉も用いられているし、言語学者らしい独自の造語もあるので、語形成や語変形などに明るくないと、意味を推量できなかったりする。余談だが、奇しくもピランデッロと同じ年にわが国で生まれた夏目漱石もまた独自の新しい言葉を作り出す名人であったことを思うと、19世紀末から20世紀初頭という激動の時代が、イタリアにおいてもわが国においても、新しい文学における言語形成という面で重要な時代を画したことに改めて思い到る。
言語学者ピランデッロが論文のテーマとしたのは郷里ジルジェンティの話し言葉であったが、ここではシチリア語について、その形成過程をたどってみることにしよう。まずその骨格はラテン語とされている。しかしそれが、ギリシア人の入植に先立つ先史時代に半島部からこの島に大挙して渡ってきたシクリ族がもたらしたものなのか、それとも前3世紀から延々と続いたローマ帝国による支配の結果なのかは定かではない。なお、シチリアという地名はシクリ族にちなむシケリアに由来し、それ以前、この島はさらなる先住民シカニ族にちなみシカニアと呼ばれていた。
そして前8世紀半ば以降、シチリアはギリシア文化揺籃の地となった。女流詩人サッフォー、詩人アイスキュロスやピンダロス、哲学者プラトンらが訪れ、抒情詩人ステシコロスや物理学者アルキメデスなどの文化人を輩出した。シチリアの沿岸部を占領したギリシア人のポリスでは何世紀にもわたり純然たるギリシア語が話され、シラクーサはギリシア世界における演劇のメッカのひとつに数えられていた。内陸部の先住民もまたその影響を少なからず受けたことであろう。また、西地中海におけるギリシア世界には南イタリア沿岸部も含まれていたので、当然のことながらイタリア語の中にはギリシア語の要素が多分に浸透した。例えば、tele- という接頭語はギリシア語の「遠い」にちなむし、-teca という接尾語は同じく「収集」からきている。
さらに、ラテン語を用いたローマ人による支配が長く続き、多くのローマ人が入植したことによりラテン語が普及浸透し、しっかりと根づいた。シチリアでは、男性名詞や形容詞の語尾を -o ではなく-u と発音することが多いが、それも -um や -us といったラテン語の名残だと考えられている。
それに続く短い蛮族支配、ギリシア語を話した東ローマ帝国の支配も多少念頭に置くべきかもしれないが、9世紀から2世紀以上に及んだアラブ時代にはシチリア語の語彙がより豊かになった。島内には今でも、カルタニッセッタ、カルタジローネなど、砦を意味する calta- を用いた地名がたくさんあるし、ソルベット(氷菓子シャルバが語源)などの食べ物にもアラビア語の名残が見られる。そして12世紀には、アラブ支配下のシチリアを、北フランス由来のノルマン人が征服したが、彼らは少数勢力であったこともあり、有能なアラブ人官僚を重用して支配した。ノルマンの宮中で、ラテン語、ギリシア語、アラビア語の三か国語が用いられていたことは、文献にも記されているし、実際、多言語の碑文も残っている。シチリアの役所で使われていたアラビア語がやがてイタリア語に浸透した例もある。シチリア王国の版図はイタリア半島南部全体に拡大したし、強力な艦隊を擁し、財政的にも軍事的にも地中海世界を圧倒していたのだから、そのような影響を及ぼしたことについては何の不思議もない。例えば、dogana はディワン(台帳、参事館)から、ammiraglio はアミール(司令官)から派生したものである。パレルモの王宮では、ビザンツ風の衣装をつけたスルタンのごとき王の身辺に国際色豊かな詩人や学者が集まり、隠喩を多用したアラブ詩の伝統が重んじられ、シチリア語は公文書に使われたのみならず、詩を記すための言葉ともなった。
 ノルマン王宮の水時計に関する碑文(パレルモ、1142年)ラテン語、ギリシャ語、アラビア語で刻まれている
ノルマン王宮の水時計に関する碑文(パレルモ、1142年)ラテン語、ギリシャ語、アラビア語で刻まれている
 フェデリーコII世(鷹狩りの書より)次のホーエンシュタウフェン家の時代、とりわけ皇帝フェデリーコ(ドイツ語ではフリードリヒ)2世の時代については、ダンテがその『俗語論』の中で「シチリアの俗語は、他に先駆けてまず名声を博した」と讃えたため、より注目されることになった。皇帝の宮廷で詠まれていた高尚なシチリアの話し言葉によるプロヴァンス風の恋愛詩の流派はシチリア詩派 (scuola siciliana)と呼ばれ、それがトスカーナの詩人たちに先駆ける動きであったというのである。だが、当時のシチリア王国は島のみならず半島南部を含んでいたし、皇帝は後半生にはプーリアに本拠を移し、トスカーナの居城やヴェネトの修道院などを転々としながら、北イタリアで教皇派と戦い続けていたし、その廷臣たちは国際色豊かであり、詩派の開祖とも目されるヤコポ・ダ・レンティーニのようなシチリア人もいたが、半島部出身者も多かったことを考えると、彼らの詩作用語は、島民の話し言葉と必ずしも同じものではなかったと思われる。また、これらの詩はトスカーナの詩人によって転写されたりしたものが後世に伝えられているため、残念ながらもとの言葉から変形をきたしている。ともあれ、文学における俗語の効用という見地から、シチリア詩派の活動は注目すべき事実であった。
フェデリーコII世(鷹狩りの書より)次のホーエンシュタウフェン家の時代、とりわけ皇帝フェデリーコ(ドイツ語ではフリードリヒ)2世の時代については、ダンテがその『俗語論』の中で「シチリアの俗語は、他に先駆けてまず名声を博した」と讃えたため、より注目されることになった。皇帝の宮廷で詠まれていた高尚なシチリアの話し言葉によるプロヴァンス風の恋愛詩の流派はシチリア詩派 (scuola siciliana)と呼ばれ、それがトスカーナの詩人たちに先駆ける動きであったというのである。だが、当時のシチリア王国は島のみならず半島南部を含んでいたし、皇帝は後半生にはプーリアに本拠を移し、トスカーナの居城やヴェネトの修道院などを転々としながら、北イタリアで教皇派と戦い続けていたし、その廷臣たちは国際色豊かであり、詩派の開祖とも目されるヤコポ・ダ・レンティーニのようなシチリア人もいたが、半島部出身者も多かったことを考えると、彼らの詩作用語は、島民の話し言葉と必ずしも同じものではなかったと思われる。また、これらの詩はトスカーナの詩人によって転写されたりしたものが後世に伝えられているため、残念ながらもとの言葉から変形をきたしている。ともあれ、文学における俗語の効用という見地から、シチリア詩派の活動は注目すべき事実であった。
その後、短いフランス人のアンジュー家支配を経て、イベリア半島由来のアラゴン家の支配、スペイン本国の支配が何世紀も続いたが、これらの支配者が用いた言葉もやはりラテン語から派生したロマンス語であることを思うと、アラブ時代のような特殊な影響を及ぼすようなものではなかったのではあるまいか。
筆者は言語学については門外漢であるので、このように大局的な見方しかできないが、たとえ言葉という切り口で見たとしても、シチリアが地中海に覇を唱えていた中世にはやはり文化のみならず言語面でも影響力が大きかったことがわかる。とくに当時の地中海は国際的な往来が激しく、その中心に位置し、文化的に開かれていたシチリアでは、アラブ、ビザンツ、ラテンなど、様々な要素が混ざり合って新しいものが生まれたのであった。
ピランデッロに戻ると、若い頃の彼がある友人に宛てた書簡に次のような一節がある。「さても私はカオスの子だ。それは寓意などではなく、まさに文字どおりの事実である。というのは、ジルジェンティの人々が、土地の言い方でカヴスと呼びならわしている、入りくんだ杜の近くの田舎で生まれたのだから。それは純然たる古典ギリシア語のカオスが訛った方言なのだから…」。
実は、この一節は、冒頭に挙げた映画の語り出しにも使われている。今でこそシチリアはイタリアの一州を占めるのどかな観光地となっているが、歴史的に見れば、それはまさに混沌としたひとつの世界、カオスの地なのであった。
![[伊検]実用イタリア語検定試験](../images/logo-iken.png)
![[伊検]実用イタリア語検定協会](../images/logo-ali.png)